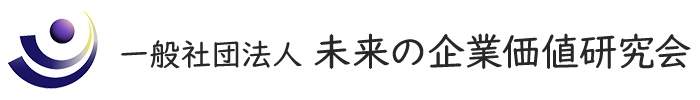宇宙投資の会は7月31日、ミニ勉強会を開催しました。テーマは「宇宙領域における官民連携とJAXA宇宙戦略基金の位置づけ」。 講師は、EY新日本監査法人の宇宙ビジネス支援オフィス所属、弁護士でもあり公認会計士でもある伏見達氏でした。
高市早苗科学技術相は4月26日、2023年に成立したJAXA宇宙戦略基金活用の基本方針を発表しました。企業や大学に10年間で1兆円規模を支援、一企業で最大500億円という大型の予算です。これによってついに日本の宇宙ビジネスも大きく前進する可能性があるのか、について詳しくお聞きすることができました。(参考記事)
ご講演の要旨
・宇宙戦略基金の技術開発テーマは「宇宙輸送」、「衛星等」、「単砂糖」、「分野共通」
・テーマ設定は日本が勝ち筋につながる推進すべき技術を取り上げ、JAXAではなく民間企業・大学等が主体となるテーマが選択されている
・実施者として大企業だけでなくスタートアップも考慮されている
・これまでの官民連携の事例紹介、①Xバンド衛星通信中継機能等の整備・運営事業、②筑波宇宙センター環境試験設備等の運営・利用拡大事業
・新しい官民連携の試案、①北海道スペースポート、②新国立競技場と愛知県新体育館の例
・まとめ「宇宙戦略基金は日本の宇宙ビジネスにとって恵みの雨」しかしこれだけでは宇宙ビジネスの前進は難しくインフラの投資と売り上げ確保が必要
参加者からの感想
・コンセッションって海外では上場企業もありますが常に政治・官に翻弄されている印象もあり、投資家としては意外にビジビリティが低く事業モデルの堅固さだけでもないかなと感じました。
・宇宙分野ではかつて半導体分野で起こったような失敗とならないよう、海外を見据えた戦略的な取組になればと願っています。もし霞が関主導がドライビングフォースなら予算をつけたところまでの花火でなく、その後がしっかりとビジネスとなるよう持続的に成長を促すことが大事だと思いました。
・金額規模は比較になりませんが日本は脱炭素でも官民でGX実行でこちらは欧米からかなり遅れ、宇宙と比べると、先頭集団に入れておらず、対処しないといけない課題が多くてまさにこれからが大変だなと感じました。
・伏見さんのお話は非常にわかりやすく、あっという間でした。日経の「私見卓見」も拝見させていただきましたが、日本の場合、宇宙ビジネスを手掛ける企業はいくつかあっても、「産業」になっていないというのはその通りかなと思いました。「自動車産業」や「半導体産業」のように、裾野を広げて関わる企業や人、投資がまわる仕組みなどがある産業とはまったく違いますね。改めて認識しました。官民連携でお金をまわしていくのはもちろん必要なのですが、国として「宇宙産業」をどうしたいのか?という強い軸が必要で、そこが今一つ見えてこない気がしています。昨日も話があった支援する政治家がいないからでしょうか?
・宇宙ビジネスを手掛ける難しさは昨日のお話の通りですが、今、2050年ネットゼロに向けて様々な技術イノベーションが必要という世界は、ある意味、宇宙と同じような状況ではないかと思いました(宇宙が特別ではなくなっているという意味)。
・プロダクトの製造やサービス提供に必要なインフラ投資が事業化のカギになると私も強く思っています。特に宇宙輸送系はこの点が大きな課題となっています。