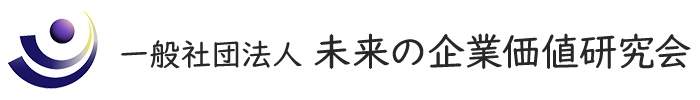宇宙投資の会は2025年4月9日、第9回勉強会を開催しました。その様子をまとめます。
<アジェンダ>
1.最近の振り返り 未来の企業価値研究会理事 鎌田氏
2.月面開発の動向と日本企業の取組み 三菱総合研究所 内田氏
3.将来の宇宙開発のために、デブリ問題の議論と方向性、その課題 宇宙開発エバンジェリスト 戸梶氏
4.ディスカッション 投資家が理解すべきこと
<サマリー>
1.最近の振り返り(鎌田氏)
今回は9回目ということで、当会も2020年10月から4年半となった。初回は理科大の木村先生からスペースコロニーの話をお聞きした。その後デブリの問題、合成開口レーダーの話、水素技術、衛星による森林の監視、衛星データの活用などを取り上げてきた。興味深かったのは「におい」の話題がでたことだ。宇宙飛行士は匂いを我慢しなければならないと、消臭フィルターを開発している方から伺った。昨年はJAXAの宇宙戦略基金(一兆円基金)のお話もお聞きした。最近の話題ではH3ロケットが初号機は失敗したものの2号機から5号機まで順調で日本の技術は十分誇れるものだと思う。iSPACEも6月に月面着陸を計画していると聞く。今回はこの月面開発の話、そしてデブリ問題と今後取り組むべき点について、お聞きしていく。
2.月面開発の動向と日本企業の取組み(内田氏)
長期をみすえてファンディングするという考え方は宇宙業界に必須。今日の話が少しでも役立てばと思う。
20年ぐらい前は宇宙というと政府の仕事ばかりだった。JAXA、経産省、内閣府といったところがプレイヤーだったが、最近は民間の異業種による宇宙ビジネスへの参入が出てきており、それらの参入コンサルなどをしている。そのほか、ispaceと共同で2016年ごろに立ち上げた民間で宇宙資源ビジネスの実現を目指した「フロンティアビジネス研究会」、また2020年ごろから政・学・産で取り組む「月面産業ビジョン研究会」などでも活動している。
宇宙ビジネスは幅広い。ロケットや衛星のイメージはあると思うが、ISSを舞台にした新薬の研究、放送ビジネス、データを受信して横断的な取り組みもある。北海道や和歌山ではロケット打ち上げ用のスペースポートの建設がなされ、一方でデブリの対策、宇宙旅行、そして月面のビジネスも位置付けられている。
火星や小惑星の探査は今でも政府が主体だが、地球のまわりは民間事業に役割分担されている。事業規模は世界で50兆円ぐらい、年2.6%で成長している。日本の市場規模は4兆円ぐらいで、政府は2030年早期に倍増することをめざし宇宙戦略基金を立ち上げた。
🔹月面について
米国のアルテミス計画は月面に関するすべてのプロジェクトのことを指し、月版の宇宙ステーションから輸送機までふくまれている。アポロ計画との違いは、最初から民間、またパートナー(外国)と一緒に取り組むことだ。アルテミス1はすでに実施しており、マネキンをのせて月を一周して地球に帰還している。アルテミス2は遅れているが来年の実施を目指し、人を乗せて月を一周(着陸なし)する。アルテミス3(2027年以降)でやっと月面に着陸という計画になっている。女性の宇宙飛行士が搭乗することになっているが、トランプ政権になった影響が懸念されている。
別途中国も月面に向けた取り組みを行っており、既に月の裏側からサンプルを採取して戻るという取り組みに成功している。アルテミス計画が西側連合になっているように、中国もロシアやUAE、ベネズエラなどの国と協力し、またその他の国にも参加を呼びかけている。
日本はSLIMが昨年の1月に、転倒した状態ではあるが着陸に”成功”した。「SORA-Q(ソラキュー)」というタカラトミー製のロボットが飛び出し写真撮影に成功した。これでアメリカ、ロシア(ソ連)、中国、インドに続き世界で五番目に月面着陸に成功した国になった。ただ着陸の精度が素晴らしく、世界初のピンポイント着陸と言われている。従来は着陸予定地の数キロ範囲内だったものが50M程度の範囲内に降りることができた。
🔹宇宙基本計画
日本の宇宙開発の取り組みは閣議決定された宇宙基本計画に従う。2023年に第5次となる宇宙基本計画が決定された。20年後をみすえて10年間の計画をたてるが、動きが早く3年で改訂となった。月面や産業新興などが新規軸となり、月面経済圏という言葉が入り、省庁横断的に行うプログラムが記載されている。また、新たに立ち上げられた宇宙戦略基金では、支援分野に「市場拡大、社会課題解決、フロンティア開拓」を求めている。また月や火星と言った人類の活動範囲拡大に向け、国際プレゼンスを確保するということで、これらの事業が2030年代早期までに10件以上でてくることをKPIとして定めている。
🔹民間企業
ispaceは2022年4月に着陸に挑戦し失敗、2025年1月に2号機を打ち上げ6月に着陸予定である。これは政府のプロジェクトではなく、自分たちでお金をあつめ顧客を集めて打ち上げたことが大変な成果。ほかにもスーパーゼネコン4社、大手自動車メーカー3社、プラント、食品、建機、玩具、素材など様々な分野の企業が活動をしている。高砂熱学工業はすでにispacceの2号機に水電解装置を搭載し月面で水電解装置を稼働させようとしており、成功すれば世界初となる。
フロンティアビジネス研究会は2016年に約10社の企業で立ち上げたが、2023年の段階で48社が加盟している。伝統的宇宙開発産業ではない企業も参加している。今年も7月18日にシンポジウムを開催する。月面産業ビジョン協議会は政学産の枠組みで立ち上げた。宇宙族と呼ばれる議員を巻き込んだ活動。2024年に「月面産業ビジョン2024」を発表した。
月面ビジネスはもう夢ではなく現実になってきている。現在は市場形成段階であり、この段階での参入は日本は従来に苦手といわれているが、長期的な視点で企業を評価し、その経営をサポートするような投資は極めて重要と考える。
3.将来の宇宙開発のために、デブリ問題の議論と方向性、その課題(戸梶氏)
地球の周りのデブリ状況はESAなどがまめにレポートを出している。10cm以上のものが34,000個あるといわれている。それ以下のサイズはトラッキングできず推測で、1cm~10cmが90万個、1cm以下は1億3000万ほどあるといわれている。800キロくらいから下はデブリがなくなっている。これは空気抵抗が大きいので早くデブリが落ちてくる。それ以上上だとなかなか落ちてこないため、数が減らない状況と考えられる。ただ密度はものすごく薄いので、デブリ問題をどうしようもない、怖い、とは思ってほしくない。とはいえ手をこまねいていていいわけではない、と思って欲しい。衛星は低軌道が多く、もうひとつは静止衛星軌道。詳しく観測したい、また燃料も節約したい場合は低軌道になる。これが2/3をしめている。ここに多くのデブリも存在している。またその発生の理由には、衛星由来のものとロケット由来のものがある。
🔹デブリの問題
人工衛星との衝突がまず挙げられる。スターリンクへの送信機は今35000円ぐらいで購入できる。普段使いには遅いが、災害などがあって地上のインフラが全てダメになった時は使うことができる。またもう少したつとスマフォから直接接続することもできるようになる。数千機の衛星があがっており、2022年〜2023年の半年間で25000回衝突回避をした。ぶつかって壊れると、それ自体がまたデブリになってしまう。
デブリの怖さはスピード。秒速八キロで周回している。それだけ大きなエネルギーでぶつかってくる。相対速度なので同じ向きであれば良いが逆から来ると大変なことになる。宇宙機器に穴が空いたり、スペースシャトルでも窓にヒビが入っていたことがあった。これがひどくなるとケスラーシンドロームという状態となり、地球から出ることができなくなる。現在のように普通に衛星の恩恵をうけて暮らしている生活を続けることができなくなる。
🔹デブリ抑制のための対策
ロケットの第1段は地上に落ちて燃え尽きるがだいたい第2段は衛星と同じ起動に入る。バッテリーや残ったエネルギーを積んでいてさらに危険。そこで余った燃料や電池を放出するという対応がとられている。
衛星は使い切ったら25年以内に落としてください(あるいは宇宙の遠くに捨ててください)というルールがあった。2022年アメリカでは5年ルールになった。日本でもアメリカでビジネスをするなら5年にする必要がある。
また最近はデブリに対し回避行動をとる設計にすることが求められている。ただこれができるのはエンジンを積んでいる場合だけ。小さい衛星ではこれをすることができない。
🔹デブリ除去のための活動
JAXAが2017年に、電流を流すテザーをISSから繰り出す実験をしたが、うまくいかなかった。2024年H2Aの上段が地球の周りをまわっていたが、これの50mまでアストロスケールの衛星が近づいて写真をとる実験を行った。この次のステップとしてこれを捕まえてどうするかを検討する。近くに行くのは簡単ではない。同じ高度を飛んでいても、どのような軌道面を飛んでいるかわからない。一度打ち上げた衛星が方向を変えるにはものすごくエネルギーが必要となる。そのために地上からレーザーを照射して落とす、あるいは衛星に発泡剤をつけて早く落とす研究、また一ミリぐらいのデブリの幕をはって落とすというアイディアを検討をしている日本の会社もある。
またそもそもデブリを出さないために、ガイドラインを作ったり国際条約の議論も進んでいる。西側の国は協力的だが、そうでもない国もある。米国では5年ルールにして厳しくしたり、静止衛星の起動に使い終わった衛星を放置した場合は罰金を課したりしている。
🔹コストと経済性の問題
1つのデブリを退けるために数百億円かかる場合、それを誰が負担をするのかという問題。何かあった時のために、保険をかけるとか、なんらかのルールが必要。またデブリとならない対策は余分な燃料をつむとか、何らかのシステム的な対応が求められ、コストがかかり収益性が損なわれる。もし投資家がこれを理解しなければ、企業も対応が難しくなる。投資家がこれを解決したいと思ってくれない限り、我々だけでは解決できない。「投資先がデブリ問題を対応している」ことを投資家に求めて欲しい。
4.ディスカッション
質問「コミュニティの中で宇宙に参入していくリスクについても議論しているか?投資家の視点だけではなくリスクの議論は重要。もし議論していればどのような内容か」
回答(内田氏)「まずは開発のリスク、次に事業のリスク。お客は誰なのか、どうやってキャッシュがまわるようなシステムがつくれるか。それからルールに関するリスク。国際条約で、地球の外は誰も占有してはいけない、となっている。でもプラントを作ろうとすれば、その土地を一定期間使わないといけない。そういったルール整備については今議論をしている。また月に人類がどんどんいって先行者利益を確保することでいいのか、すぐに月に行けない国の利益は考えなくて良いのか、という問題もあり、いろいろなリスクについて話している」
質問「月面開発で、みな一番いいところを取りたい、ということで、ただいまの国際情勢をみていると難しくなっているのではないか?」
回答(内田氏)「例えば、発電に太陽光を使うということで、日照率のいいところをみな狙いたい。そういう土地は限られる。アルテミス3では着陸予定地を13箇所も出した。その後中国も着陸予定地を発表しいくつか重なっていた。この先不安な点である。どこかで話し合いが必要。国連で月の開発、宇宙資源の利用についてルールを考えようという動きが2年前から始まっている」
質問「日本企業の強みを教えて欲しい」
回答(内田氏)「層の厚さ。米国はスタートアップ企業などが目立っているが、様々な企業がいるという意味においては、日本が秀でている。また月面への輸送費が高額な状況において、小さく性能がいいものを作ることにおいては、日本企業は強みがある。」
質問「戸梶さんにお聞きしたい。燃料放出してしまって宇宙空間の汚染にならないのだろうか」
回答(戸梶氏)「通常の燃料放出が宇宙空間において問題になる”汚染”を引き起こすことはない。宇宙はほぼ完全な真空であり、非常に広大であるため、放出された物質はすぐに拡散して極めて薄く広がることで濃度が低くなり、宇宙環境に対する影響は無視できるレベルとされている」
感想「日本での取り組みも進展している印象を持った。ただ、デブリの問題、国際協調が前提となっている取り組みは、現在の政治状況だとなかなか難しいという感想も持った。このあたりサステナブルファイナンスの課題ともオーバーラップしている」
質問「内田さんのご説明の中で、日本政府がKPIとしてたてている参入企業2030年代10件というのは、控えめではないか?」
回答(内田氏)「ミッション・プロジェクトに参画というのをどのレベルとみるかにもよるところがありますが、国プロだけではおそらく10件に満たないことが予想され、そうなるとと海外政府からの受託や短期的な回収が難しい中での自社投資等が必要となりますので、そこまで簡単な目標ではないと考えています。」
5. クロスオーバー部会
(宇宙産業にスタートアップが多いということから、なんとかそれらに投資をできないかということで、クロスオーバー部会では金融庁とも意見交換しながら活動している)ついにクロスオーバーファンドを立ち上げた野村アセットの今村氏から状況報告。
今村氏「ご縁があり外部のVCと組んで昨年の7月にスタートアップ投資室を立ち上げ、ディープテック領域でインパクト型のクロスオーバー投資をはじめた。社会課題を解決するための必要な技術やソリューションをきちんと世の中に送り出し実装することが重要。初期のころはCVCや助成金などもあり資金調達手法に幅があるが、日本では海外と違い、上場が近くなると資金の出し手が極端に少なくなる。そこを支援しようと考えた。資金規模は50~60億円。宇宙にだけ特化しているわけではないが、今いくつかの宇宙ベンチャーがソーシングに含まれている。問題は、宇宙産業に限らないが、長期のエクイティストーリーがない会社が多いこと。上場を目指しても長期で何を目指すのか定義できていない。そうすると長期投資家の機関投資家に相手にされず、個人投資家中心のスモールIPOになる。日本の宇宙ベンチャーは今4社ぐらい上場できたが、バリュエーションへの織り込み方が未だ確立されていない。セルサイドアナリストもついたのでこれからこなれてくるかもしれないが、SAR衛星関連のところなどは防衛の観点で目先のビジネスの蓋然性も高いが、光学衛星や画像などのソリューション系は、民間や海外に打って出ないといけないこともあり、評価に難航している。確固たるビジネスモデルがないまま上場してしまうと時価総額が伸びず、上場後のファイナンス戦略も含めその後の成長が難しい。上場が資金調達の一部みたいになっている会社もある。日本の宇宙ビジネスを発展させるためには上場をどのように位置付けるかも重要」
内田氏「最近上場した企業は、ispace、アストロスケールといった宇宙ベンチャーが始まった時から活動している企業で、大きな絵を描いていた。スタートアップの数は増えているが、最近でてきている企業は、若干小さな規模が多い。事業として成立させようとすると、どうしてもはざまに着目をし、そうなると思う。ただ初期の頃の企業はマーケットがない時から、マーケットを作る取り組みをしていたので、今後もそのような視点を持つことが必要なのかもしれない」
クロスオーバー部会・松本部会長「私は個人にも、このように長期の成長を共有する機会があればと思っており、クロスオーバー投信が出せるようになったことは良かったと思う。まだ課題があるが、引き続き議論していければと思う。のちほど直近の課題点をまとめて共有する」
まとめ(鎌田氏)「これからの課題や取り組むべき点がよく理解できた。また投資家サイドの課題も共有できた。今後投資家が宇宙開発企業を応援していけるよう、取り組みを続けていきたいと思う」
6. 終了後、メールで寄せられた質問・感想
「戸梶さんの仰る通り、市場なき市場を目指すところにこそ活路があると改めて感じました」
「IPOでは日本の場合サイズ的に資金調達しても、さほどの大きさにならないというのは仕方がないと思いました。同盟諸国間で、日本の役割分担をより明確にしていく方向で、他国が着手しづらい分野で取り組むしかないのではとも感じました」
「今村さんのコメントに近いですが、補助金や政府への売り上げに頼らない成長を描いてもらえるとわかりやすいので従来よりも積極的に発信して欲しいと思います」
「デブリの発生リスクや衝突回避の頻度をリアルタイムでモニタリング・可視化する国際的な仕組み(共通データベースやリスクスコア化など)はどのようなものでしょうか?」
代表的なものとして下記のような国際的な仕組みがあります。
- 欧州宇宙機関(ESA)の「Space Situational Awareness(SSA)プログラム」
ESAは、宇宙空間の状況把握を目的としたSSAプログラムを推進しており、デブリの追跡や衝突リスクの評価、再突入予測などを行っています。これにより、運用中の衛星や将来のミッションに対するリアルタイムの支援が提供されています。
参考:(ESA - The story so far - European Space Agency
- NASAの「Conjunction Assessment Risk Analysis(CARA)」
NASAは、衛星の衝突リスクを評価するためのCARAを運用しており、衝突回避のためのポリシーやガイダンスを提供しています。これにより、運用中の衛星の安全性を確保しています。
参考:(Conjunction Assessment (CA Home) - NASA
- 欧州連合(EU)の「Space Surveillance and Tracking(SST)」
EUは、宇宙物体の監視と追跡を行うSSTシステムを構築し、デブリの検出、カタログ化、軌道予測を行っています。これにより、運用中の衛星の衝突リスクを軽減するためのサービスが提供されています。
参考:(EU Space Surveillance and Tracking - European Commission
「デブリ除去や発生防止に取り組む企業に対する経済的インセンティブの現在と、将来の見立てをお伺いできれば幸いです」
経済的インセンティブの現在と、将来の見立ては下記のとおりです。
現在のインセンティブ:
- 政府による資金提供と契約
日本のAstroscaleは、宇宙デブリ除去技術の開発・実証に対して、日本政府からの資金提供を受けています。また、Astroscaleは、英国やフランスの宇宙機関とも契約を結び、宇宙デブリ除去ミッションを進めています。デブリ除去を行う企業はどこも技術開発の段階のため、政府による資金援助に頼る傾向にあります。
参考情報: (Astroscale Japan Awarded Grant of up to U.S. $80 Million by ...)
将来の見通し:
- 市場ベースのインセンティブの導入
宇宙デブリの除去や発生防止を促進するため、リサイクルボンドやデブリ除去への補助金の導入が検討されています。これにより、企業が持続可能な宇宙活動を行う動機付けとなることが期待されています。
参考情報: (Market-based instruments to incentivize more sustainable practices ...)
- 国際的な規制と協定の整備
宇宙デブリ問題への対応として、国際的な規制や協定の整備が進められています。これにより、宇宙活動における持続可能性が確保され、企業がデブリ除去や発生防止に取り組むための明確な枠組みが提供されることが期待されています。
詳細情報: (Space Debris - UNOOSA)